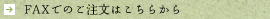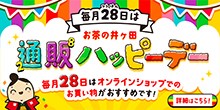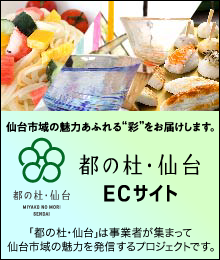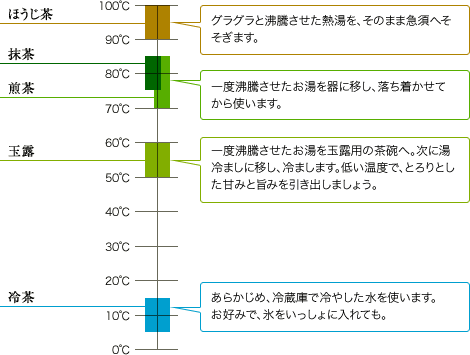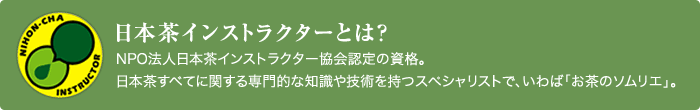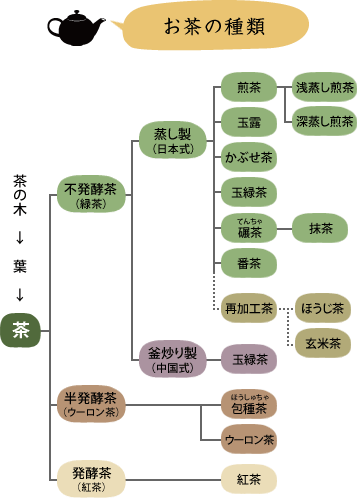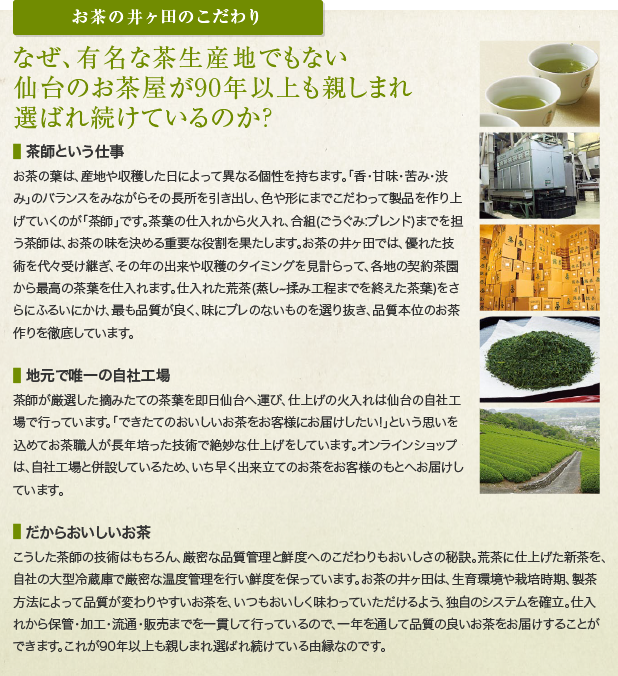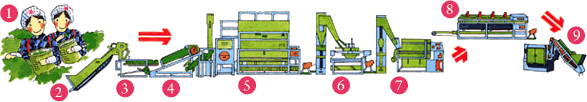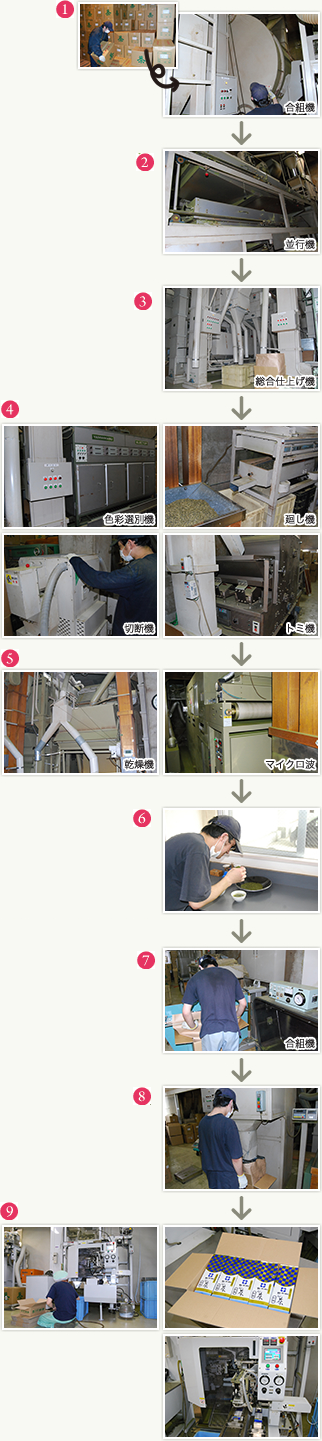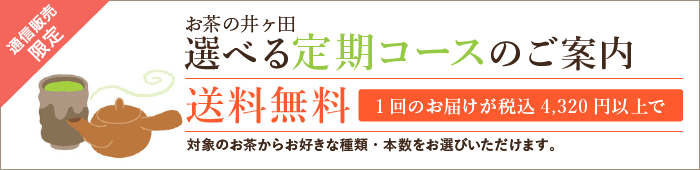お茶の種類・効能
お茶で健やかな日々を。
『お茶は養生のための貴重な薬であって、長生きするのに必要なものである・・・』 (栄西禅師の「喫茶養生記」より)
毎日が健康でイキイキしているって、素晴らしいこと。その健康維持に役立っているのが"緑のお茶"なんですね。 アルカリ飲料の王様、"お茶"の効用は、私達の体に良いことが科学的に証明されています。
さあ、一服のお茶で、心も体もリフレッシュ!
お肌若々しく、お茶はビタミンの宝庫
“色白は七難隠す”といいますが、メラニン色素の沈着を防いでくれるのがビタミンC。 お茶には、熱に強いビタミンCがたっぷり。 さらにビタミンA、B、Dなども含まれ、美肌を保ちます。 お茶はまさに、美容飲料といえますね。
コレステロールは、お茶で大掃除
動脈硬化をひきおこすコレステロールを体外に排出するのに活躍するのがビタミンC。 食事の後に、ビタミンCがたっぷりのお茶が効果的。
高血圧を防ぐ、お茶の効き目
お茶のカフェインは、心筋の働きを良くし血行を旺盛にします。 又腎臓からの尿の排泄を促す利尿作用があることから、高血圧や心臓病の方に良い影響を与えるといわれます。
老化を防ぐ、お茶のタンニン
渋味の成分"タンニン"には、細胞内の脂質が酸化するのを防ぐ強力な働きを持っています。 20代から始まる老化…毎日頂くお茶で予防に一役。
疲労回復にも一役
血液の循環を盛んにする強心作用と利尿作用を持つお茶のカフェインは、疲労回復にも大活躍。 お仕事やスポーツの後に味わう一服のお茶。健康な暮らしへの知恵です。
スマート美人の秘密
さらに、お茶のタンニンには、脂肪の代謝を促進する作用と、腸の働きを活発にして便通を良くする作用があるのをご存知ですか。 スッキリボディラインの秘密は、食後の一服のお茶ですね。
たばこ1本、お茶一服
ヘビースモーカーはビタミンCが不足がち。 これはたばこのニコチンを解毒するのに多量のビタミンCが消費されるため。 たばこを吸った後は、お茶でビタミンCを補給。(特に一煎目が豊富です。)
お茶の制ガン効果
よくお茶の産地はガン(とくに胃ガン)の死亡率が全国平均より低いといわれています。 それはお茶のタンニンに、発ガン性物質を抑制する働きがあるといわれるからです。 上質のお茶でガンを予防。
二日酔いの特効薬、上級煎茶
お茶のカフェインは、大脳の働きを呼びさまし、その利尿効果によって、アルコールを早く体外に排出させます。 二日酔いの朝、ご主人にはちょっと濃いめのお茶を。奥様の優しい心づかいですね。
井ヶ田のお茶一覧
深蒸し茶
美しい緑の水色、まろやかな甘味、深いコク。
浅蒸し茶
新茶の香りを生かしたフレッシュな味わい。
有機栽培茶
大自然そのままの旨味とコクが自慢のお茶。
ほうじ茶
深い味わい、心やすらぐ香りの良さが自慢。
玄米茶
煎茶に玄米をブレンド、香ばしい玄米の香り。
玉露・抹茶
手間と愛情がかけられた贅沢な味わい。
鳥龍茶・番茶
健康効果の高い成分を多く含んだお茶を。
芽茶・粉茶・くき茶
おいしさいろいろ、お茶の世界を広げて。