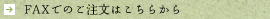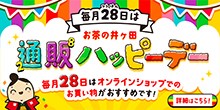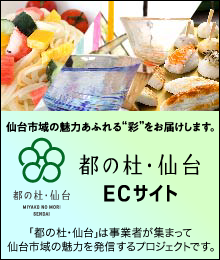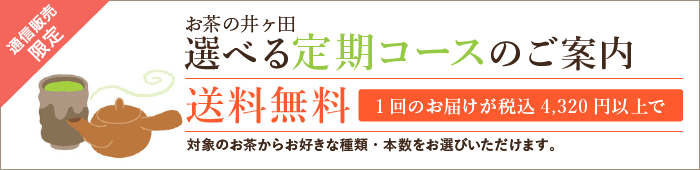和スイーツの通販・お取り寄せ|お茶の井ヶ田オンラインショップ喜久水庵
伊達の粋を、お茶に込めて 四季―新茶の香り
ご注文・お問合せ 電話・TEL 0120014123(フリーダイヤル) 受付時間 9:00-18:00(月~土)※日曜・祝日休み
-
- 喜久福という、しあわせ。
- 大好評の理由は?
お茶屋のこだわりをご紹介。 - [喜久福全商品一覧]
- [1種詰合せ]
- 抹茶
- 生クリーム
- ずんだ
- ほうじ茶
- [2種詰合せ]
- 抹茶×生クリーム
- 抹茶×ずんだ
- 抹茶×ほうじ茶
- 生クリーム×ずんだ
- 生クリーム×ほうじ茶
- ずんだ×ほうじ茶
- [4種詰合せ]
-
- 喜久水庵おすすめギフト
- 用途別・商品別に
お選びいただけます。 - お祝い・記念日のギフト
- 内祝のギフト
- ご挨拶・手土産のギフト
- ご仏用のギフト
- お茶のギフト
- お茶とお菓子のギフト
- お菓子のギフト